定額減税の確定申告の書き方が「分からない?どうやって書けばいいの?」こんな不安をかかえてる人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が、定額減税の確定申告の書き方を分かりやすく丁寧に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
定額減税の確定申告の書き方
最初は、定額減税の確定申告の書き方についてです。
定額減税については、確定申告書の書き方を理解しておかないと、大変なことになることを覚えておきましょう。
第一表の書き方
次は、第一表の書き方についてです。
確定申告書の第一表の44番の令和6年分特別税額控除の欄に定額減税の金額を記入することになります。
第二表の書き方
次は、第二表の書き方についてです。
確定申告書の第二表の配偶者や扶養親族に関する事項の一番右のその他に番号2番と記入することになります。
書き漏れがあった場合
次は、書き漏れがあった場合についてです。
確定申告書の第一表及び第二表の書き漏れがあった場合には、定額減税額の控除が認められなくなります。
(注)定額減税額の控除を受けるためには、書き漏れがないようにしなくてはなりません。
確定申告書の書き方が理解できたら、復習のために定額減税の概要について、今一度解説します。
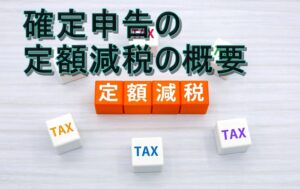
確定申告の定額減税の概要
次は、確定申告の定額減税の概要についてです。
令和6年度の税制改正に伴い、所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
確定申告の定額減税の対象者
次は、確定申告の定額減税の対象者についてです。
確定申告の定額減税の対象者は、令和6年分の確定申告の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人です。
確定申告の定額減税の実施時期
次は、確定申告の定額減税の実施時期についてです。
事業所得(個人事業主)等の確定申告の定額減税は、2024年分の確定申告時期(2025年2月から3月)に実施されることになります。
確定申告の定額減税額の計算
次は、確定申告の定額減税額の計算についてです。
確定申告の定額減税額は、次の金額の合計額です。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者又は扶養親族1人につき 30,000円
(注)合計額がその人の令和6年分の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額を限度とします。
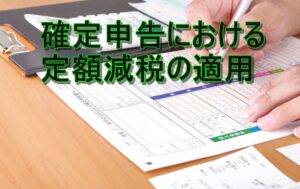
確定申告における定額減税の適用
次は、確定申告における定額減税の適用についてです。
所得税の確定申告が必要な人や医療費控除等を適用して還付を受けるための申告を行う人については、令和6年分の所得税の確定申告の際に定額減税を控除して計算を行います。
給与所得者の場合
次は、給与所得者の場合についてです。
給与所得者については、年末調整において定額減税を踏まえて計算されているため、年末調整をしていれば、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者であっても、確定申告が必要な場合もあります。
その場合、確定申告において、最終的な定額減税額の計算をして所得税の金額を精算することとなります。
公的年金所得者の場合
次は、公的年金所得者の場合についてです。
年金所得者に係る申告不要制度(注1)に該当する場合には、確定申告は不要です。
ただし、定額減税額が異動する場合(注2)は、確定申告において、最終的な定額減税額の計算 をして所得税の金額を精算することとなります。
(注1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(注2)例えば、令和6年中の扶養親族等の人数が増加した場合など
給与と公的年金の両方で定額減税を受けている場合
次は、給与と公的年金の両方で定額減税を受けている場合についてです。
支払いを受けた給与等と、公的年金等の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告は必要ありません。
事業所得者等の場合
次は、事業所得者等の場合についてです。
事業所得者や不動産所得者の方などは、確定申告の際に所得税の額から定額減税額を控除します。

不足額給付金の取り扱い
次は、不足額給付金の取り扱いについてです。
定額減税額の金額が控除できなかった場合の取り扱いについてです。
不足額給付金の概要
次は、不足額給付金の概要についてです。
令和6年分の所得税の確定申告において、所得税額から定額減税額の全てを控除できなかった場合には、その金額は、給付されることになります。
これを不足額給付金といいます。
不足額給付金の金額
次は、不足額給付金の金額についてです。
不足額給付金の金額は、その金額の万円未満を切り上げることになります。
例えば、所得税108,000円で定額減税額が120,000円の場合には、不足額給付金の金額は、20,000円になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税の確定申告の書き方」について悩んでいる人のために
「損をしないための書き方」についての解説
- 定額減税の確定申告の書き方
- 第一表の書き方:44番の令和6年分特別税額控除の欄に定額減税額を記入
- 第二表の書き方:配偶者や扶養親族に関する事項の一番右のその他に番号2番と記入
- 書き漏れがあった場合:定額減税額の控除が認められない
- 確定申告の定額減税の概要
- 確定申告の定額減税の対象者:居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人
- 確定申告の定額減税の実施時期:令和6年分の確定申告の申告時期
- 確定申告の定額減税額の計算:本人3万円+扶養親族等1人につき3万円
- 確定申告における定額減税の適用
- 給与所得者の場合:年末調整をしていれば確定申告不要
- 公的年金所得者の場合:扶養親族の異動があった場合には、確定申告で定額減税を精算
- 給与と公的年金の両方で定額減税を受けている場合:両方で受けていることだけでは、確定申告は必要なし
- 事業所得者等の場合:確定申告の際に定額減税額を計算
- 不足額給付金の取り扱い
- 不足額給付金の概要:>控除できなかった金額は、給付される
- 不足額給付金の金額:万円未満を切り上げ
この記事を書いた想い
今回、「定額減税の確定申告の書き方|損をしないための書き方を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税の確定申告の書き方が、分からない?どうやって書けばいいの?」という質問をよく受けるので、それならば、定額減税の確定申告の書き方について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、定額減税の概要や確定申告における定額減税の適用について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、定額減税の概要や確定申告における定額減税の適用について詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
コメント