確定申告の減価償却の耐用年数が「分からない?どうやって決めればいいの?やり方が分からない?」こんなお悩みを抱えている人も安心してください。確定申告が得意なベテラン税理士が、確定申告の減価償却の耐用年数や減価償却のやり方について分かりやすく丁寧に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
減価償却のやり方
最初は、減価償却のやり方についてです。
事業などの業務のために使用される建物や備品などの資産は、一般的に時の経過等により価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
確定申告の計算において取得価額が10万円以上の減価償却資産については、購入時の経費とはせず、一定の期間において経費に算入していきます。
これを減価償却費といいます。
減価償却費の計算
次は、減価償却費の計算についてです。
減価償却費の計算は、下記のように計算されます。
取得価額×償却率(注1)×12分の使用開始日から期末までの期間(注2)
(注1)償却率は、耐用年数に応じて決められています。
(注2)1か月に満たない端数がある場合には、1か月として計算します。
取得価額
次は、取得価額についてです。
取得価額は、その資産を実際に取得するために直接要する金額をいいます。
消費税の額は、納税者の経理方式により含まれるか含まないかを判定します。
耐用年数
次は、耐用年数についてです。
耐用年数は、耐用年数省令により資産ごとに法定耐用年数が決められています。
使用開始日
次は、使用開始日についてです。
減価償却資産を取得しても実際に業務に使用するまでは、減価償却費は発生せず、業務のように使用を開始した「使用開始日」から減価償却費が発生します。

耐用年数の概要
次は、耐用年数の概要についてです。
新品と中古品で耐用年数は変わってきます。
法定耐用年数
次は、法定耐用年数についてです。
法定耐用年数は、耐用年数省令により資産の種類や構造、使用目的などにより細かく定めています。
新品の耐用年数
次は、新品の耐用年数についてです。
新品の減価償却資産を購入等した場合には、耐用年数省令に基づいて法定耐用年数が定められています。
中古品の耐用年数
次は、中古品の耐用年数についてです。
中古品の減価償却資産を購入等した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
また、使用可能期間の見積もりが困難である場合には、簡便法により算定した年数によることができます。

所得税法と法人税法の減価償却の違い
次は、所得税法と法人税法の減価償却の違いについてです。
所得税法における減価償却でも法人税法での減価償却でも減価償却の計算方法には、別段の違いはありません。
しかし、減価償却の取り扱いについては、違ってきます。
所得税法の減価償却
次は、所得税法の減価償却についてです。
所得税法の減価償却は、原則定額法になります。
届け出をすれば、定率法での減価償却もできます。
所得税法の減価償却は、強制になります。
どういうことかというと、事業主が減価償却をしない場合においても減価償却があったものとして翌年以降の減価償却の計算をすることになります。
法人税法の減価償却
次は、法人税法の減価償却についてです。
法人税法の減価償却は、原則建物は、定額法その他の減価償却資産については定率法になります。
その他の資産については、届け出をすれば、定額法での減価償却もできます。
法人税法の減価償却は、任意になります。
どういうことかというと、減価償却するかしないかは、法人が任意で決められるということです。
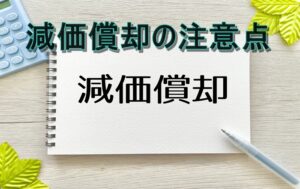
減価償却の注意点
次は、減価償却の注意点についてです。
減価償却をする場合には、いくつかの注意点があります。
年の途中で購入した資産の減価償却
最初は、年の途中で購入した資産の減価償却についてです。
減価償却資産を年の途中において取得し、事業のように供した場合には、通常の減価償却の計算をした後に事業のように供した月から12月までの月数案分をしなければなりません。
事業用と家事用の両方共有の資産の減価償却
次は、事業用と家事用の両方共有の資産の減価償却についてです。
個人事業主の場合に、減価償却資産を事業用と家事用の両方で使用しているような場合には、合理的な方法により案分した事業用の減価償却だけが必要経費に算入することができます。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の減価償却の耐用年数」で悩んでいる人のために
「減価償却のやり方や耐用年数」についての解説
- 減価償却のやり方
- 減価償却の計算:取得価額×償却率×12分の使用開始日から期末までの期間
- 取得価額:その資産を実際に取得するために直接要する金額
- 耐用年数:耐用年数省令により資産ごとに法定耐用年数が決められている。
- 使用開始日:実際に業務のように使用を開始した「使用開始日」から減価償却費が発生
- 耐用年数の概要
- 法定耐用年数:耐用年数省令により資産の種類や構造、使用目的などにより決定
- 新品の耐用年数:耐用年数省令に基づいて法定耐用年数を決定
- 中古品の耐用年数:その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数
- 所得税法と法人税法の減価償却の違い
- 所得税法の減価償却:原則定額法、減価償却は強制適用
- 法人税法の減価償却:原則建物は定額法その他は定率法、減価償却は任意適用
- 減価償却の注意点
- 年の途中で購入した資産の減価償却:取得日から期末までの期間で月数案分
- 事業用と家事用の両方共有の資産の減価償却:事業用の部分だけを経費算入
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の減価償却の耐用年数|減価償却のやり方耐用年数を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の減価償却の耐用年数が、分からない?どうやって決めればいいの?やり方が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の減価償却の耐用年数について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、減価償却のやり方や耐用年数などについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、減価償却のやり方や耐用年数などについて詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
コメント